梅棹忠夫『文明の生態史観』
1957年(昭和32年)に『中央公論』に発表された梅棹忠夫の論考である。(Wikipediaより)
本書は、梅棹先生の中央アジアの調査旅行を元に文明に対する新しい見方を示したもの。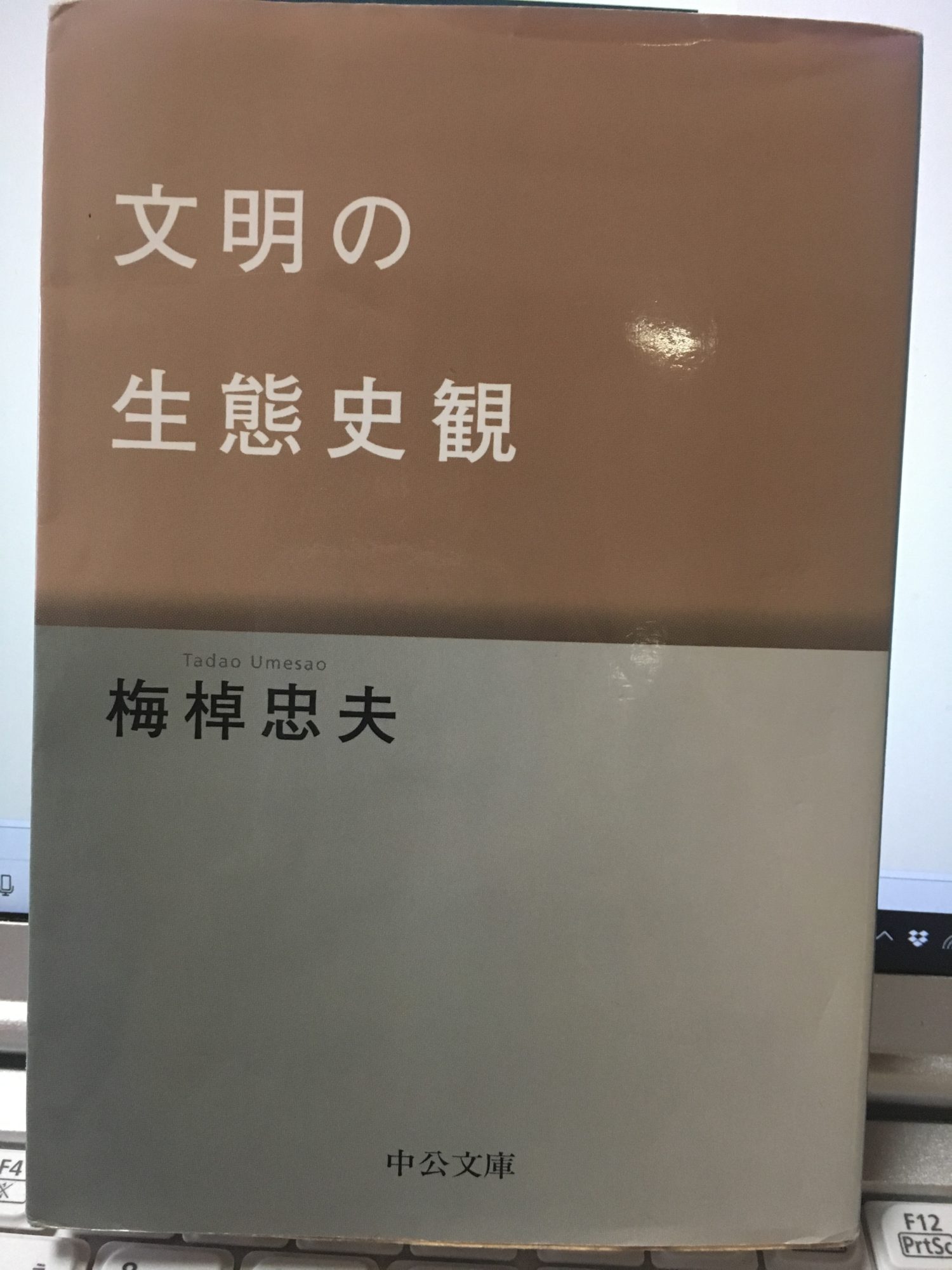
従来の「西洋と東洋」という枠組みによって世界を区分するのではなく、第一地域と第二地域という区分で文明を説明したもの。
西ヨーロッパと日本は第一地域に属する。ユーラシア大陸はを第二地域としている。
第二地域は古代文明が発展した地域ではあるものの、たびたび騎馬民族等の外部からの攻撃により破壊が繰り返されて没落していった。
その攻撃により政治がたびたび脅かされ、高度な政治体制を築けないため、専制政治となる。専制政治でブルジョアが発達せず、資本主義社会の妨げになった。
そして、強力な軍隊を築けぬまま。軍国主義時代には植民地となってしまう。
一方、第一地域では、気候が温暖でかつ辺境の地域だったため、外部からの攻撃に会わず、第二地域よりは発展が遅いものの第二地域から文化を輸入し発展。安定高度な社会を形成した。
辺境の地域に位置していたため、第二地域が砂漠の民に脅かされるような危険がない。それがブルジョアを育てた封建制度を発展させて、資本主義体制へと移行した。
統計的なアプローチが全くない。定性的な展開で明快さがない。というのも「べき」論ではなくて「かくあるザイン)」の理論という主張である。
非常に難解な課題図書でした。
投稿者プロフィール
-
人財育成、技術系社員研修の専門家。東京都市大学特任教授。博士(工学)。修士(経済学)。専門は「電力システムネットワーク論」著者に「IEC 61850を適用した電力ネットワーク- スマートグリッドを支える変電所自動化システム -」がある.ブログは映画感想を中心に書いている。
詳細プロフィールはこちら。
